今号は高知大学地域協働学部須藤順ゼミのみなさん([大学院2回生]柳原伊吹さん、[2回生]泉雅也さん、松原彩耶香さん、宮澤詩織さん)が取材に同行してくれました。
学生の立場からまなざす食の生産現場をレポートとして掲載します。
大川村が「はちきん地鶏」に出会うまで
大川村は、高知県北部、愛媛県との県境に位置する、四国山地の標高1000m級の山々に囲まれた緑豊かな村である。
人口は約400人と少ないが、かつてここには鉱山があり、最盛期の昭和30~40年代には従業員が2000人ほど生活しており、村全体では4000人程いたという。
しかし、鉱山の閉鎖が決まる。
それと同時期に早明浦ダムが完成し、村の中心部がダムの底に沈んでしまった。
大川村にとってこの2つの出来事の影響は大きく、鉱山で働いていた従業員や村中心部に住んでいた住民が村を離れることになったという歴史がある。
結果的に、現在世間で騒がれている人口減少問題に数十年も前から直面している地域となったのである。
かつての大川村の主産業は林業であったが、外国産の建築資材の台頭により産業として維持をすることが困難になっていた。
産業の衰退、人口減少による税収の低下を少しでも食い止めるために目を付けたのが畜産であった。
しかし、大川村には平地がほとんどなく、山を切り開いて牧場となる土地を確保する必要があり、「大川黒牛」の生産に取り組むにはまず山を開拓するところから始まった。
その後、牛だけでは出荷サイクルがゆっくりであることから、比較的出荷までのサイクルが短い鶏の生育も検討されるようになり、当時高知県が「土佐はちきん地鶏」の試験場となる地域を探していたことから、大川村で生産を開始した。
大川村がはちきん地鶏と出会った瞬間だった。
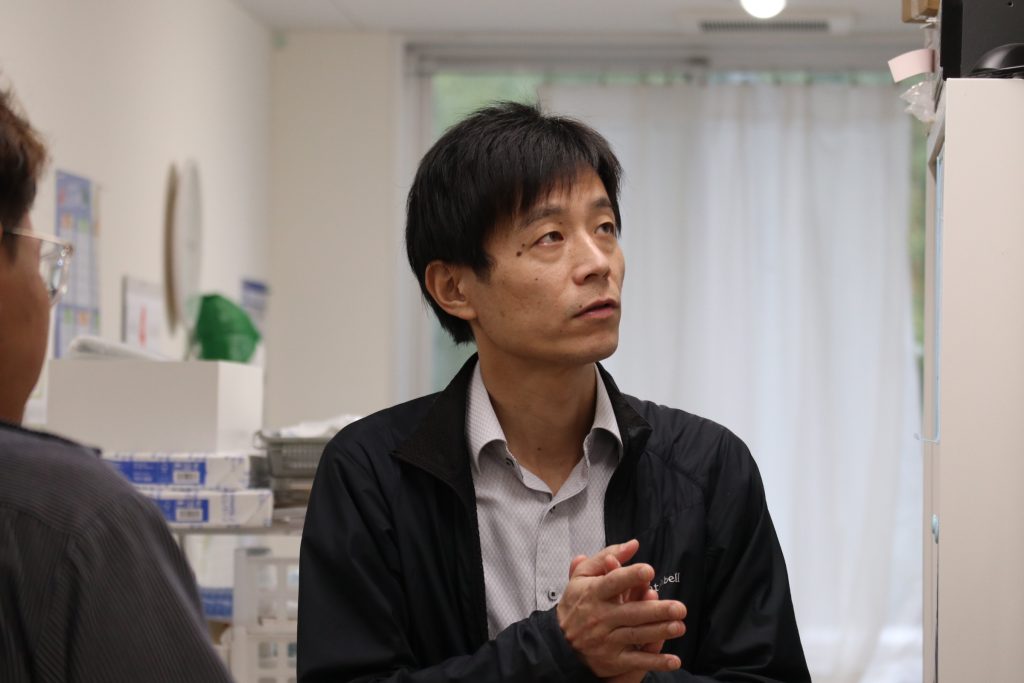
土佐はちきん地鶏は高知人の気質を表している…?
土佐はちきん地鶏は、祖父に「土佐九斤」祖母に大軍鶏それらを掛け合わせて生まれた父の「九斤シャモ」と母の「白色プリマスロック」を交配させることによって生まれた種だ。
こうした血統を持つことによって風味・肉質に優れる。
「改良したりするのがすごく好きな県民性から生まれたと思います」と語るのは一般社団法人大川村ふるさとむら公社の平賀さん。
「元々日本人は朝顔や鯉など品種改良を行い美しさを求めることを古くから行ってきました。高知人にもその傾向はあると思いますね。例えば『土佐犬』もそうです、掛け合わせて強く勇敢な犬を育て上げたからこそです。『土佐はちきん地鶏』もまさに同じで、いかに美味しい鶏にするか…という試行錯誤の結晶なんです」
親鳥を掛け合わせて品種改良を行い、個性を磨いていく地鶏産業が、緑豊かで病気やウイルスのリスクが低い畜産向きの環境であった大川村で発展していったのは必然だったのであろう。
今では、高知県内で生産されるはちきん地鶏の8割が大川村産となっている。
ちなみに土佐はちきん地鶏の「はちきん」は土佐弁で“負けん気の強い男勝りな女性”の性格を表す言葉だ。
そして、「土佐はちきん」をよく読んでみると「とさはちきん」
…「土佐はチキン」!
日本鶏の主たる34品種のうち8種が高知県原産。
まさに土佐といえばチキンで、鶏王国であることを示すような名称でもある。

食べものの生産現場と背景を知ること
そもそも、「地鶏」とはどのようなものか。
在来種由来の血統が50%以上で、1㎡あたり10羽までの平飼い(土佐はちきん地鶏は“はち”きんにかけて8羽)で75日以上(ブロイラーの2倍)の日数をかけて飼育されたものを地鶏と呼ぶ。
地鶏は食肉鶏全体のわずか1%の生産量である。
「一般的な鶏肉(ブロイラー)」や「銘柄鳥」と比べて、大量生産が難しく自然体に近い環境で育てられる。
「大量生産しようとすると、成長促進の薬を飲ませたり、ゲージに入れて育てたりすることもあります。もちろん僕たちの暮らしはそうやって育てられた鶏がスーパーに並ぶことで供給を絶やさず成り立っているので一概に良い悪いでは判断できません。でも、命をいただく以上それまでは健康的にのびのびと育ってほしいという想いがあります。運動量が確保することでストレスを和らげることができ、弾力のある肉になります」。
平賀さんは「地鶏、銘柄鶏、ブロイラーのそれぞれの特色や生産の背景を知った上で選ぶことが大切」だという。
「いつもはブロイラーだけど、人を招く時には地鶏にしてみようとか、シーンや気分、志向に併せて手に取っていただきたいです」。